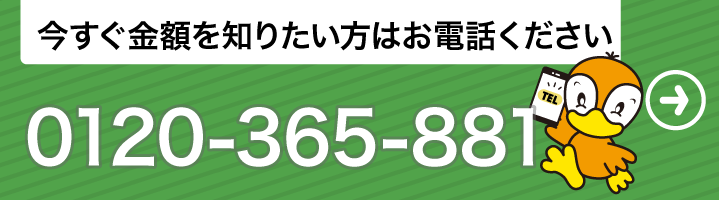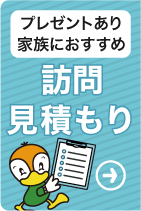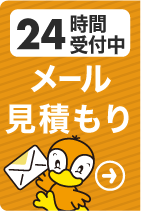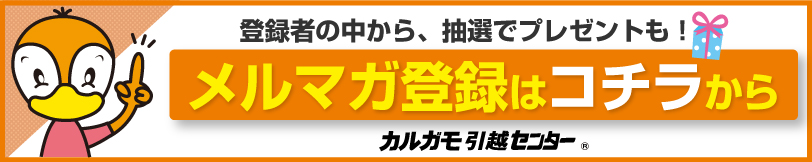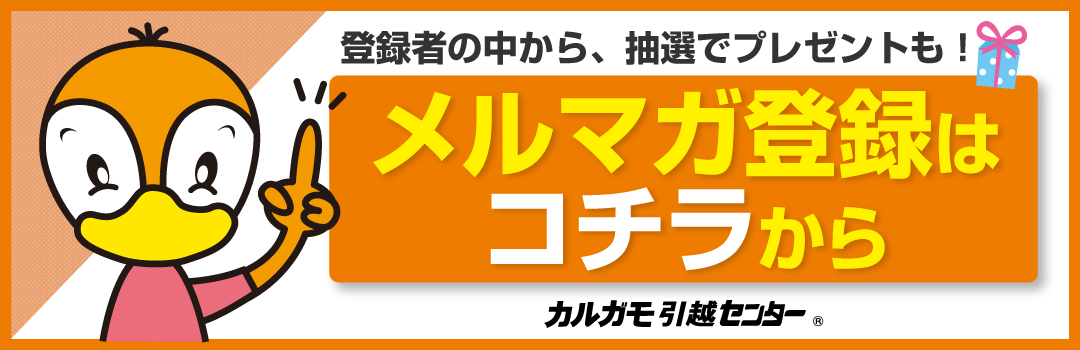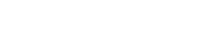旧居を退去するときに心配になるのが、敷金に関するトラブルです。
返金が遅かったり、どのくらいの値段が返ってくるのかが実際に返金されるまでわからなかったり、心配になることが多いことでしょう。また原状回復費用に対する認識が借主と貸主の間で異なってしまうと、思いがけず敷金が返金されないという事態に陥ってしまうこともあります。
敷金を返金してもらいたいけれど、どのように交渉すればよいのかわからず、最終的に貸主の請求に応じてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
実は原状回復費用の中には借主の負担にならない金額も存在しており、法律やガイドラインの内容をしっかり把握しておかないと、余計な費用を支払ってしまう可能性もあるのです。
そこで今回は敷金の概要について礼金や不動産会社の仲介手数料との違いからおさらいし、敷金が返金されるタイミングや返金される金額の相場、敷金の払い戻しを請求する方法などについて徹底解説します。
参考になる法律やガイドラインについてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
敷金についての基礎知識

「敷金」は聞き慣れた言葉かもしれませんが、意外とその意味を理解していない方も多いのではないでしょうか。まずは敷金の基礎知識から解説していきます。
敷金の意味
敷金とは、借主が賃貸物件を貸してもらうときに貸主に預ける保証金です。賃貸物件を借りるときの初期費用のひとつとして知られています。
賃貸物件を貸す側は、借主が家賃を滞納したり、部屋を損傷させたりするリスクに対処しなければなりません。そこで事前に担保金を集金して、万が一のケースに備えているのです。その担保金こそが、敷金。入居中に特にトラブルがなければ、敷金は借主にそのまま返金される仕組みです。
ただ、最近では敷金の支払いが不要な物件も増えつつあります。年々の人口減少によって空き家物件となる可能性が高まり、貸主たちは入居者のハードルを下げる必要性が生じているからです。
しかし敷金という名目の料金はなくとも、清掃費やクリーニング費などを高く設定して補填している可能性もありますので注意しましょう。
敷金がゼロとはいえ、最終的に費用が高くなってしまえば本末転倒ですよね!賃貸契約の際には敷金以外のコストも見落としなく確認することが大切です。
礼金や仲介手数料との違い
敷金と同様に代表的な初期費用として知られているのが礼金です。礼金は入居するときに貸主に謝礼として支払うお金。相場としては家賃の1か月分~2か月分となっています。
退去時に返金されない点が敷金との大きな違いです。こちらに関しても近年は空き物件を避けるため、ゼロに設定している物件も多く見受けられます。
また、それ以外の初期費用として仲介手数料という言葉も耳にしたことがあるでしょう。
賃貸に関する仲介手数料とは、物件を契約する際に不動産会社に支払う手数料のことです。物件の案内や重要事項の説明、契約の締結などの対価として支払います。敷金と同様に返金されない点に気をつけましょう。
敷金はいつ・どれくらい返金される?

敷金が「返金されるお金」ということはご説明しましたが、いつ・どれくらい返金されるのかが一番気になるところでしょう。ここからは敷金が返金されるタイミングや敷金の返金額の仕組みについて解説していきます。
敷金が返金されるタイミング
敷金が返金される時期に関しては、これまで法的なルールが明確に定められていないのが実情でした。そのため、敷金の返還時期は当事者間で締結する契約の内容によって決まることが一般的だったようです。
しかし令和2年施行の改正民法によって、賃貸借の敷金に関する条文が追加され返還時期について以下の規定が設けられることとなりました。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
引用:民法 第四款 敷金 第六百二十二条の二 (e-Govポータル)
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
部屋を退去したにもかかわらず敷金返還が明らかに遅いときは、契約内容を見落としなく確認したうえで、不動産会社や貸主に法律の根拠を提示しつつ確認してみるとよいでしょう。
敷金の返金額
敷金の返金額に関しても民法の規定に記載されています。
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
引用:民法 第四款 敷金 第六百二十二条の二 (e-Govポータル)
ここには賃貸借に基づいて生じた債務の額を控除した残額と記載があります。したがって、債務の額が大きくなればなるほど返金される敷金の金額が下がることがわかるでしょう。
ちなみに敷金の返金額の平均は5万円ほどだといわれています。
敷金に関する法律やガイドライン、具体例
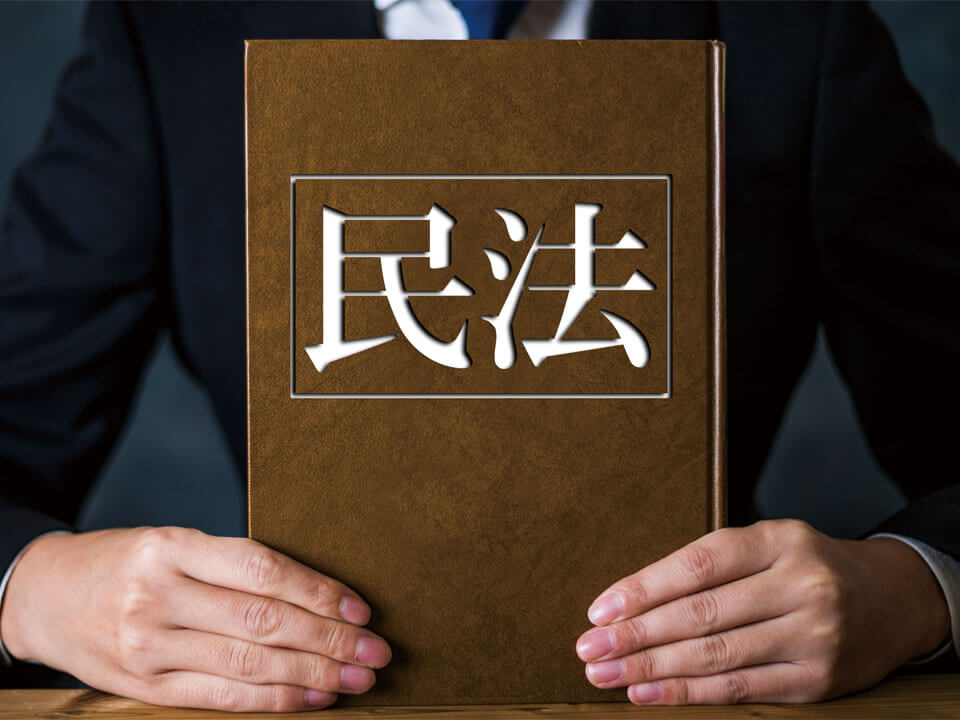
敷金についてさらに正確に理解するには、ルールや根拠を把握しておくことが大切です。この章では敷金に関する法律やガイドラインについて解説していきます。原状回復費用を支払わなければならない具体例や、敷金の返金を要求できる事例も参考にしてみてください。
民法
敷金に関するルールは民法の各条項で明文化されています。詳細を確認してみましょう。
民法621条
敷金の返金に大きく関わってくるのが「原状回復費用」という概念です。原状回復費用に関するルールは民法621条に記載されています。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
引用:民法 第三款 賃貸借の終了 第六百二十一条(e-Govポータル)
記載には物件の損耗や経年変化を除くとあり、一般的な使用方法で生じた損傷などに関しては原状回復義務がないことがわかります。
つまり故意や過失、善管注意義務違反などの責任をともなう損傷でなければ敷金から引かれる必要はないのです。
原状回復について不当な要求を受けたときは、民法621条を根拠に話し合いを進めるとよいでしょう。
民法622条
民法622条では、敷金返還債務発生前における敷金の効力に関する記述も明文化されています。
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
引用:民法 第四款 敷金 第六百二十二条の二(e-Govポータル)
つまり物件を借りているときに家賃を支払えなくなってしまった場合、貸主は家賃滞納相当額を敷金から差し引けます。
しかし借主の立場からは、敷金を家賃に補てんするよう貸主に対して請求することはできません。敷金を支払ったからといって滞納をしていいというわけではないのです。
原状回復に関する国土交通省のガイドライン
原状回復に関するトラブル解消を目指して、国土交通省もガイドラインを公表しています。敷金に関するトラブルというのは非常に多く、問題視されているということがわかりますね!
ガイドラインでは、原状回復を下記の通り定義しています。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
引用:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省住宅局)
このように、原状回復について、物件を借りた当時の状態に戻すことではないと明確に記しています。
Q&Aコーナーで敷金の意味をわかりやすく解説しているのも親切です。民法の難しい条文を読むのが負担に感じる方は、国土交通省のガイドラインを一度チェックしてみるとよいでしょう。
原状回復費用を支払わなければならない具体例
故意や過失、善管注意義務違反、通常の度合いを超える使用などによって発生した損傷や汚れについては、原状回復費用を負担しなければなりません。
手入れを怠ってしまった場合
手入れを怠ったケースとして、部屋の掃除を怠って発生したシミや汚れなどが該当します。冷蔵庫下の錆を放置したり、クーラーからの水漏れを放置したりした場合など、具体的な事例はさまざまです。
そのほか、日常のメンテナンス不足で付着した台所のススや油などにも注意しなければなりません。
原状回復費用の支払い義務が発生しないように、物件の各設備を日ごろからきちんとメンテナンスすることが大切です。
子供やペットによって汚れた場合
子どもやペットのいたずらによって物件を汚してしまったときも、同様に原状回復費用の対象となります。落書きや柱のひっかき傷をはじめ、臭いの付着にも注意しなければなりません。子どもやペットがいるご家庭は、このような事態を予防することが大切です。
例えば、はがせるウォールステッカーを壁に貼っておくのが有効な対策です。また子供には壁を傷つけないように言い聞かせる、ペットであれば爪とぎやトイレのしつけを事前にしておくなどの基本的なことも怠ってはいけません。
ただ、子どもやペットと暮らす場合、予想外のいたずらによって、事前に預けておいた敷金でも損失を補えない恐れもあります。原状回復費用の増加も想定して、あらかじめ資金を多めに確保しておくとよいかもしれません。
不注意によって破損させた場合
こちらには日常生活における床の色落ちや壁の破損などはもちろんのこと、引っ越し作業で生じた傷も含まれます。大きな家具などは無理に自分で運び入れたりせず、信頼できる引っ越し業者に任せることでリスクは防げるでしょう。
そのほか、鍵の紛失あるいは破損による取り換えなども原状回復費用とみなされます。鍵をなくさないように、保管場所を決めたり目立つキーホルダーを導入したりするなど、管理方法について工夫しておきましょう。
通常の使用に該当しないケース
喫煙によるヤニでクロスが変色したり臭いが付着したりした場合も、通常の損耗には該当せずに原状回復費用が求められます。
タバコを吸う方は、日常的に室内での喫煙を避けたりベランダや換気扇の下で喫煙するなど工夫して極力壁などの汚れを抑える必要があるでしょう。
敷金の返金を要求できる例
退去時に修繕・清掃が必要になった場合でも、借主が費用を支払わず敷金の返金を請求できることがあります。
通常の住み方でも発生するトラブル
通常の住み方でも発生するトラブルに関しては、貸主の負担になる可能性があります。
たとえば、家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置のあとが挙げられます。また、意外に思われるかもしれませんが壁に貼ったポスターによるクロスの変色や、日照による畳の変色も含まれます。
ただ天井に直接取り付けた照明器具の跡や、重量物をかけるためにあけた壁の釘穴などは、通常の住み方の範囲外になる恐れがあります。通常の住み方の定義に関しては貸主と考え方を事前にすり合わせておくと、トラブルが減らせるでしょう。
建物の構造により発生するトラブル
建物の構造的な欠陥により発生したトラブルに関しては、貸主の負担になる可能性があります。たとえば過去に、建物のカビや異臭を巡って敷金の返還を求める訴えが提起された事例がありました。
その原因は建物の構造上の問題で、結露が起こりやすかったこと。そのせいでカビが発生したということで、判決では借主に過失があったとは認められませんでした。結果、貸主に対して敷金の返還が命じられています。
そのほか、構造的な欠陥によって生じた畳の変色やフローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂なども借主の責任にはならない可能性があります。
建物の構造が破損や汚れなどの原因なのであれば、貸主にその旨を伝えて敷金の返還を請求してみるとよいでしょう。
入居者確保に必要な修繕やメンテナンス
入居者確保に必要な修繕やメンテナンスに関しては、貸主の負担となります。
たとえば、次の入居者を確保するために行う網戸の交換や風呂釜の取り換えなどが挙げられます。また、フローリングのワックスがけやトイレの消毒なども該当するでしょう。
少しでも心当たりのある費用があれば、貸主に確認してみてください。
東京都では借主の保護が進んでいる?

東京都内の物件を検討している方も多いかと思います。
そこで朗報をひとつ。実は東京都は、特に借主の保護が進んでいるエリアとして知られているのです。
この章では東京都が定めている賃貸トラブル防止に関するガイドライン「東京ルール」について、概要をご説明していきます。
東京ルールの概要
2004年10月、東京都内で「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」が施行されました。これこそが通称「東京ルール」。賃貸物件に関する退去時のトラブルを防ぐことを目的として作られた条例となります。
こちらの施行にあわせて、わかりやすくその内容をまとめた賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf)が策定されており、退去時の敷金精算や入居期間中の修繕に関する費用負担の原則などが記載されています。
なおこちらは条例となるので、東京都以外には適用されません。
それでは東京ルールのポイントとして、退去時の費用負担や入居中の設備修繕費用に関する決まりを確認してみましょう。
退去時の費用負担
賃貸住宅トラブル防止ガイドラインでは、トラブルの起こりがちな退去時の費用負担について、具体的な事例を紹介しています。
たとえば、クロスの一部を借主が破損してしまった事例。破損部分だけを修理すると、ほかの部分とクロスのカラーが違ってしまいます。
ガイドラインでは、破損した部分を含む一面分に関しては借主の負担となることがあり、色を統一させるための全体の補修に関しては貸主の負担になるという見解を示しています。
このように借主が費用負担する場所の単位について、細かく挙げられているのがとても親切です。たとえば、畳は原則1枚単位、クロスは原則m²単位、鍵は補修部分と明記されています。ちなみに鍵を紛失してしまったときは、シリンダーの交換も含むとのことです。
そのほかにも、借主と貸主によって見解が異なってしまいそうな負担箇所についてもたくさん紹介しています。敷金を巡るトラブルを回避するうえできっと役立つでしょう。
入居中の設備修繕費用
ガイドラインでは、貸主は借主が住宅に居住するのに必要な修繕をする義務があるとしています。
「必要な修繕」とは具体的に、借主が通常の使用において支障をきたさないよう修繕することだと解説されており、修繕の必要性は物件の構造や築年数などの要素を総合的にみて判断するのが一般的とのことです。
ただしやはり、借主に故意・過失などの責任がある修繕に関しては借主の負担としています。
また、家賃が低いにもかかわらず修繕に多額の費用が発生するときは、例外的に貸主の修繕義務が免除されることもあるようです。家賃が低い物件を借りる際には知っておくべき知識だといえるでしょう。
ガイドラインでは、小規模な修繕に関して借主、貸主のどちらが費用を負担するかの例も一覧で示されています。
敷金の返金を請求する方法

法律やガイドラインが整備されつつあるとしても、敷金に関するトラブルがなくなるわけではありません。ここからは万が一のケースに備えて、敷金の返金を請求する方法について解説していきます。
管理会社や大家さんと直接交渉する
管理会社や大家さんに敷金の返金について交渉を行います。
ただ、やみくもに交渉しても敷金の返金についての妥当性を示せなければ、うまく思い通りに進まない恐れがあります。
そのため敷金の返金を請求している理由をわかりやすく伝えられるように、あらかじめ要点や根拠をまとめておくことが大切です。
たとえば相場より高い金額の清掃費が請求されていたり、畳を1枚しか汚していないのに複数枚分の請求がきている場合などはその事実が書かれた請求書や相場の根拠などを用意しておきましょう。
異なる見解をお互いに押し付けあっても、交渉が平行線をたどってしまいます。明確な根拠を示せれば、敷金の返金に納得してもらえるかもしれません。民法や国土交通省のガイドラインも相手に提示しつつ、有利に交渉を進めましょう。
内容証明郵便の送付
敷金の返金について交渉したけれど、返金に応じてもらえないようであれば、内容証明郵便を送付するのも有効な手段です。
内容証明郵便とは、書類を出した事実、日付、内容などを証明できる郵便物のこと。発言の有無に関するトラブルを防止するのに役立ち、クーリングオフや貸金の督促状などに用いられることもあります。
これを送ることで相手に心理的な圧力がかかり、敷金の返金に応じる可能性も高まることでしょう。
この場合の内容証明郵便には、敷金を支払っている事実や貸主から送付された見積書の金額、借主が本来負担すべき費用、請求する金額、入金先口座などを記載するのが基本です。
返金を強く望んでいることを示すため、返金期限や法的措置の検討を記載することもあります。自分のおかれた状況や事情に応じて、不足ない内容を記載していきましょう。
少額訴訟
内容証明郵便を送付しても敷金が返金されない可能性もあります。その場合に検討できる手段が少額訴訟。
これは原則として一度の期日で審理を完了して判決を下す簡潔な訴訟手続きです。60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用することができます。
手数料が数千円で比較的安いほか、弁護士を立てずに訴訟を起こせるので、敷金の返金を巡るトラブルでは頻繁に活用される傾向にあります。
少額訴訟では、被告となった立場からは反訴を起こせないのも大きな特徴です。たとえば大家さんが借主から敷金の返金を請求された裁判において、借主に対して修繕費用の支払いを請求する訴えを起こせません。
いずれにせよ裁判は大ごとな出来事だと感じ、あまり前向きには検討しづらいかもしれません。しかし少額訴訟は手続きが簡易的で、迅速な解決を目指せる訴訟手続きです。最終手段として知っておいて損のない選択肢でしょう。
敷金の返金に関するトラブルを防ぐ対策

敷金の返金を巡って貸主との間でトラブルが起きると、お互いにストレスを感じることになります。敷金を返金してもらえる可能性もありますが、事前にトラブルを防げるに越したことはありません。
ここからは敷金の返金を巡るトラブルを防ぐ対策について解説していきます。
トラブルになりやすいポイントを把握する
シンプルな対策方法として、トラブルになりやすいポイントをあらかじめ把握しておくことが大切です。トラブルになりやすいポイントとしては畳や襖、ペット、タバコ、住宅設備が挙げられます。
畳・襖
一般的に入居者を確保するための設備交換費用は貸主の負担です。ただし、畳の表替えやふすまの張り替えなどの費用が契約書で入居者負担として定められているケースもあり、注意しなければなりません。
たとえば、畳1枚あたり5,000円の場合、枚数が10枚であれば5万円のコストが発生する可能性があります。畳の枚数が多ければ負担もそれなりに大きくなってしまうでしょう。
もし契約書に入居者の負担だと明記されていた場合、畳と同様に襖の枚数も確認したうえで最大どれくらいの費用が発生するのかを予想してから契約を考えるようにしましょう。
ペット
基本的にペットによる損傷は、借主の負担となっているケースが多い傾向です。
たとえば契約の際に、ペット飼育を条件に「敷金全額償却」への合意が求められることがあります。つまり入居時に支払った敷金が返金されることはないということです。
一度同意をしてしまうと借主の敷金一部返還請求は不当だとみなされますので、トラブルにならないように注意しましょう。
タバコ
一般的に一般的な度合いを超えた使用による消耗は、借主の負担とされる傾向があります。
タバコに関しては、クロスがヤニで変色したり臭いが付着したりしているのであれば、通常の使用による汚損を超えると判断されることが多いです。
したがって喫煙者の方は、クロスの変色や臭いの付着に十分配慮しながら物件を利用する必要があるでしょう。
また、事前の取り決めで喫煙が禁止されている場合は用法違反に該当する可能性もあるので注意してください。
住宅設備
すでにご説明したとおり、手入れを怠った場合にも原状回復費用の支払いが求められることがあります。
たとえばキッチンのシンクに空き缶を放置したり、洗面台にヘアピンを放置したりしてサビの跡がついてしまうことがあります。このような汚れは非常に落としづらく、のちのち原状回復費用として自分の首を締める結果となってしまいますので、面倒くさがらずにゴミ捨てや生活用品の管理を行っていきましょう。
そのほか風呂やトイレの水垢をはじめ換気扇の油汚れなども、清掃を怠った結果としてみなされます。
契約前に書類で特約をチェックしておく
敷金には特約が定められるケースがあります。敷金の特約とは、原状回復の原則とは異なる契約内容で、物件退去時の費用を借主に請求する約束です。
たとえば室内のクリーニング費用は、次の借主のために貸主が負担するケースが一般的です。しかし、敷金の特約によって借主の負担にできる場合もあるということです。
畳やカーペット、フローリングなどに関しても、特約によって借主の負担とされるケースがあり、注意が必要です。
なお、原状回復に関して借主に不利な内容の特約は、必ずしも有効であるとは限りません。
特約が成立するには、特約に客観的かつ合理的な必要性がある前提のもと、借主が特約による修繕の義務を認識して義務負担の意思表示をする必要があります。
敷金の特約に関する詳細は契約書に記載されるので、契約の際には見落としなく確認するようにしましょう。
入居前に部屋の状態を把握する
退去まで物件を慎重に利用していたとしても、入居前から傷や汚れがあれば入居者の責任にされてしまいかねません。
つまり入居中に発生した損傷や汚損でないとはっきり証明ができないと、原状回復義務によって費用の支払いが求められてしまうのです。
この対策としては入居前に物件の最終チェックをするのが望ましいです。損傷や汚損を発見したときは不動産業者の担当者に対応をお願いします。また部屋に汚れがあった際には何枚か写真に残しておくと非常に有利になると思われます。
入居前にチェックすべきポイントとしては、床や壁の汚れ、キッチンの排水溝の流れやすさ、トイレ・浴槽の割れ、窓の開け閉めの具合が挙げられます。
玄関に関しても鍵の具合やチャイムの音なども見落としなく確認しましょう。
退去時の立ち会いに参加する
一部の不動産業者では、退去をするときに立ち会いが不要とされる場合もあります。しかし原則として、敷金の返還に関するトラブルを回避するには立ち会いに参加するのが無難です。
賃貸における退去時の立ち会いは、部屋の損傷や汚損を確認して、修繕に関する責任を明確にするプロセスです。所要時間は一般的に20分~40分ほど。一般的に借主と不動産業者、大家さんなどが立ち会いに参加します。
入居時からついていた損傷があれば、トラブルを防ぐためにもこのときに明確に主張する必要があります。また修理負担の内容に納得できなければ、曖昧にせず根拠を説明してもらうことも大切です。
引っ越しでは仕事や体調不良などが原因で、代理人に退去の立ち合いを依頼するケースもあります。しかしトラブルを減らすためには、自分で立ち会いに参加するに越したことがありません。その際は日程の変更ができないか貸主に相談しましょう。
敷金バスターを活用する
とはいえ皆さんは敷金や賃貸物件に関する専門家ではありません。やはり不動産会社や貸主よりは知識が不足しているわけで、理不尽にも説得されてしまうのではないかと不安を感じることでしょう。そこで頼れる味方が敷金バスターです。
敷金バスターとは、内閣府認証特定非営利活動法人である日本住宅性能検査協会が派遣する立ち会い人です。スタッフは敷金診断士と呼ばれており、賃貸物件の退去時に物件の使用状況や修繕費用を適切に見積もり、客観的に原状回復費用を提示してくれます。
取引実績は2,000件以上を超えており、平均8割の敷金が返還されているとのことです。相談料は無料であり、個人や法人の立場を問わず、気軽に相談できるようになっています。
敷金返還までの流れとして、まずは電話や専用フォームなどから悩みを相談します。共有した情報をもとに、依頼のあった地域を担当するスタッフから連絡がもらえるので、詳細を伝えるとともに退去の立会日程を調整しましょう。
退去立会日までに室内の撤去や清掃を済ませておき、退去立会当日にはスタッフが原状回復工事費用の概算を調査してくれます。最終的に貸主から提出される見積額の妥当性までチェックしてくれるので、安心して退去のプロセスを進めていけるでしょう。
敷金バスターのHPへはこちらから!
まとめ

今回は敷金の概要をはじめ、敷金が返金されるタイミングや返金される金額の目安、返金を請求する方法などを解説させていただきました。
敷金は基本的に、通常想定される使用の範囲内で物件を利用していれば全額返還されるはずです。ただしメンテナンス不足による汚損、不注意による破損などだと、修繕費用の負担を求められるケースもあるので注意しましょう。
また慎重に物件に住んでいたつもりでも、借主と貸主の間で費用負担の責任を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。不当に原状回復費用が求められていると感じた際には、民法や各地域のガイドラインなどを根拠にしながら、敷金の返金交渉を行うとよいでしょう。
敷金に関するトラブルが起きてしまえば、気持ちよく新生活をスタートできません。敷金に関する疑問を解決してから、引っ越しを進めていきましょう。
カルガモ引越センターも敷金返還交渉サービスを提供!
引っ越しにともない敷金の返還交渉が必要になったとき、カルガモ引越センターにも相談できます。
カルガモ引越センターでは、敷金バスターと協力して敷金返還のサポートを行っています。高額な修繕費用の請求や、一方的な立会査定などで困ったとき、トラブルを解決してくれます。
電話や専用フォームなどで申し込みを受け付けているので、敷金の悩みがある方はぜひカルガモ引越センターにご相談ください。