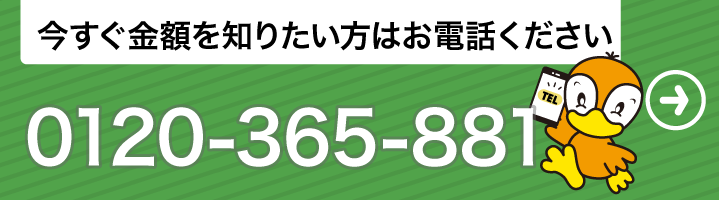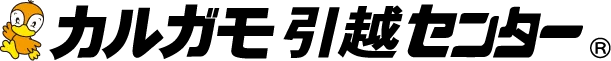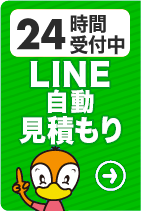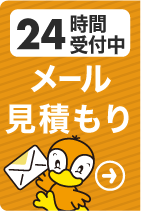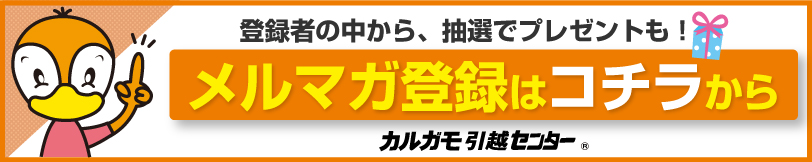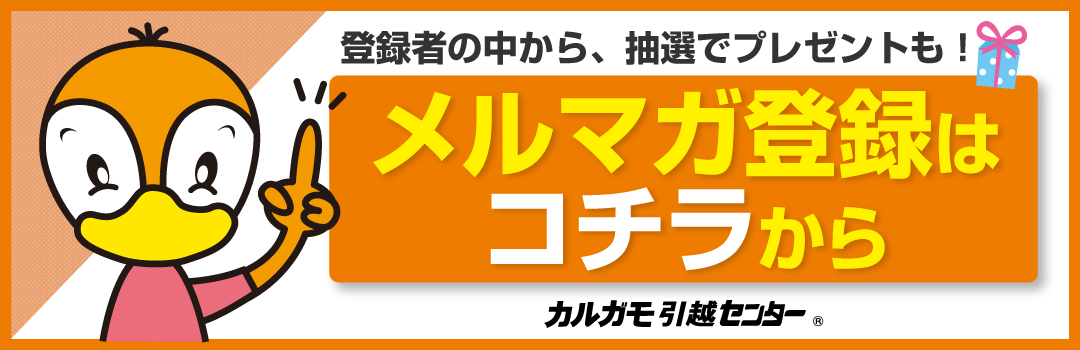この記事を読んでいる方は、引越しをしたいけれど大きくのしかかる初期費用の負担に悩んでいらっしゃるのではないでしょうか?
もっと家賃の安い部屋に移動しなければならなくなった。子供たちが大きくなって、もっと広い家が必要になった。様々な事情があると思いますが、そこには必ず引越し費用の問題がつきまといます。
しかしそのままの状態を継続していると、月々の過剰な家賃によって家計破綻を招いてしまったり、子どもたちに不自由な思いをさせてしまったりする恐れがあるでしょう。一度そうなってからではなかなか手の打ちようがありません。
事情にもよりますが、深刻であればあるほど引越し費用が大きな負担になるという理由で引越しを諦める必要はありません。実は国や自治体、さらに都道府県や市町村には住まいに関する助成金制度・補助金制度が用意されているからです。しかしその存在はあまり広く知られてはいません。
これらの助成金制度を理解しておかなければ、取り返しのつかないほどの大きな損をしてしまうこともありえます。そのため、住まいに関する助成金制度・補助金制度について理解を深めておきましょう。
この記事では、住まいに関する助成金制度・補助金制度をご紹介します。経済的な理由で引越しを諦めている方は、ぜひこの記事をご参考にしてください。

↑↑バナーをクリックして読者様アンケートへ!是非あなたの体験をお聞かせください☆
こんな状態ならば引越しを考えるべき

引越しの初期費用はたしかに大きな負担となります。しかし、現在の部屋に住み続けることの方が危険である可能性もあるため注意してください。
まずは一度、ご自身の家庭の状態を客観的に振り返りましょう。実際にどのような状態ならば引越しを検討するべきなのでしょうか?ここでは引越しを検討すべき状態についてご説明します。
家計の状況が変わって家賃の負担が大きくなった
家賃の目安は、手取り収入の1/3程度と言われています。家賃負担が手取り収入の1/3以上を超えてしまうと、家計を圧迫してしまうため注意してください。
例えば手取り収入20万円の方の家賃目安は約6.7万円ですので、手元に残る13.3万円を生活費に充てることになります。もしこれ以上に家賃がかかってしまうと食費や水道光熱費などにかなりの節約をしなければ、貯金に回すお金は残せないでしょう。病気や怪我などの医療費や冠婚葬祭費の突然の出費にも耐えることは難しくなります。
無理のある家賃を支払い続けることは家計破綻を招く恐れもあるため、家賃の負担を抑えるためにも引越しを検討しましょう。
近年、物価高や不安定な雇用状況の影響で、家賃の支払いが難しくなったり、住まいを失うリスクに直面している方が増えています。頼れる親戚が近くにいない、引越し資金の目処が立たないという状況でも、「住宅確保給付金」という制度を活用することで、引越しや住まいの確保が可能になるケースがあります。
家族が増えて今の家の広さでは暮らしづらくなった
お子さんがまだ赤ちゃんのときは、さほど部屋の広さは必要ありません。たとえ小さめの1Kのお部屋でも子育ては物理的には可能となります。しかし立って歩くようになるとみるみるうちに活発になり、少しはしゃいだだけでも物にぶつかって怪我をしてしまうような可能性も出てきます。
さらに二人目のお子さんが生まれた際には確実に日常生活が不自由になってしまうでしょう。そのような場合、家族全員の健康な毎日を考えれば可能な限り引越しをしないといけない状況だといえます。
時間の流れとともに必要な住まいの広さというものは変化するもの。このままでは暮らしづらくなったという悩みを抱えるようになる前に、いちど助成金のことを調べた上で引越しを検討してみるべきです。
助成金対象となる条件とは?

助成金制度は、条件に該当する対象者が利用できる制度になっています。では実際にどのような方が対象者となるのでしょうか?ここでは住宅に関する助成金制度の対象者になりやすい方の条件をご紹介します。ぜひ、ご自身が該当するかをチェックしてみてください。
子育て世帯
まず子育て世帯は、住宅に関する助成金制度の対象になりやすいです。
子育て世帯とは、これから結婚する若年夫婦や18歳未満の子供を扶養・同居している世帯のこと。日本は少子高齢化が問題視されており、国内の出生率を上げるために、さまざまな子育て支援サービスが提供されています。
各自治体では「出産育児一時金」や「医療健診」、「小児医療援護制度」などさまざまな子育て支援サービスが提供されています。各自治体で支援内容は異なりますが、子育て世帯の引越しや住宅に関する支援を実施しているところもあります。
子育て世帯の方に対して手当が手厚く支給されているため、一度は住所を管轄する市区町村の役所に出向いて、活用できる助成金制度がないかを尋ねてみましょう。
また、まだ子供を産んでいない新婚の夫婦世帯、そしてこれから結婚する予定のカップルも「子育て世帯」として政府の支援対象となります。
経済的な理由で結婚に踏み出せない低所得者の方々を対象にした助成金・補助金制度も用意されていますし、新婚世帯の家賃や敷金礼金、引越し代など新婚生活にかかる費用を補助する制度もあります。
新婚世帯が活用できる助成金制度(補助金制度)は、39歳以下といった年齢制限や世帯年収の条件などが設定されていますが、一度でいいので条件に該当するかを確認してみることをおすすめします。
新婚世帯が活用できる助成金制度は、年内に結婚した人が限定など諸条件が細かく定められています。申請タイミングを過ぎてしまうと、条件の対象外になるかもしれません。そのため、結婚を視野に入れた段階で速やかに活用できる助成金制度がないかを確認してみましょう。
ひとり親世帯
生活様式が多様化していく中で、近年はひとり親のご家庭も増えてきました。ひとりで子どもを育てるということは想像もおよばないほど大変なことです。よって乳幼児や児童を抱えたひとり親に対して、生活の安定のための支援金や手当が国や自治体から行われています。
ひとり親世帯に向けた助成制度としては「児童扶養手当」や「自立支援教育訓練給付金」、「母子寡婦福祉資金」などがあげられるでしょう。また家庭相談サービスなども提供されているので、ひとり親の方で困ったことがあった際は気兼ねなく自治体に相談をしてみてください。
引越しに関する助成金費用としては「母子家庭等家賃助成金制度」という制度を用意している自治体があります。助成金制度の条件に該当すれば家賃の一部を補助してもらえますので、ぜひ自治体が定める条件に該当しているかをチェックしてみてください。
高齢者の方
年々日本では核家族化が進み、孤立して暮らす高齢者の方が増えてきました。独居の高齢者が貧困や怪我により孤独死してしまうケースも増えてきており、このような悲しい問題を解決するために高齢者を支えるための取り組みが自治体をあげて推進されています。
そのひとつの施策が「高齢者向け優良賃貸住宅」です。国と自治体が家賃の一部を負担してくれるだけではなく、高齢者が住みやすいバリアフリー設備の住宅を紹介してもらえます。
年齢や世帯年収などの条件はありますが、もし離れて暮らす高齢者のご家族がいらっしゃって、その方がお引越しを考えている場合はこちらを視野に入れてもらうといいでしょう。
障がい者世帯
身体障害や知的障害、精神障害(発達障害)のある方がいらっしゃる世帯に対してもこの国には手厚い支援サービスが用意されています。
「特別障害者手当」などの経済的支援のほか、「自立訓練支援」や「就労継続支援」など勤労をするための訓練支援が有名ですが、実は自立した生活のために住まいに関する助成金も自治体によっては用意されています。
お住まいの地域によって支援内容は変わるため、利用できる助成金制度とその対象についてはお住まいの地域で一度ご確認してみてください。
親世帯との近居を考えている方
今後自分たちがどのような子育てをするかを考えた結果、親世帯の協力を得るため近居を考える方が増えています。親世帯との近居を検討する方が増えた主な要因は、共働き世帯の増加です。
子どもが熱を出したため、学校に迎えに行かなければいけないなどのような場合でも、親にお迎えを頼めるため子育ての負担が減らせます。また親が所有する自動車を借りられるため駐車場や車の維持費をかけずに自動車に乗れるなど、経済的支援を受けている方も増えているようです。
また親が高齢になったことによる介護・見守りの必要性から、その近くに住むことを希望する子世帯も増えてきました。施設やヘルパーなど第三者の手をあまり借りずに、できるかぎり自分たちで面倒を見たいという方が多いのです。
当然、転居には費用がかかります。しかしそんな親世帯との近居を考えている方に向けた「親元同居近居支援補助金制度」という制度もあるのです。
10年以上居住する意思を持って転居する必要があるなど、諸条件は細かく定められていますが、助成金を活用できれば少ない費用で引越しが可能となります。知らないで全額自費となってしまうのはかなりもったいないことですので、親世帯との近居を検討する前には一度自治体へ相談をしてみましょう。
失業中・収入が低い方
労働の意思や能力があるにも関わらず、仕事に付けていない失業中の方や収入が低い世帯に対しては、生活困窮者自立支援法に基づき「住居確保給付金」が受けられます。
離職や廃業の収入減で住居を失う可能性がある方を対象に、最長9カ月間の家賃相当額の支援金を支給する給付金です。
近年の物価上昇や雇用環境の不安定さにより、仕事を失った方や収入が大きく減少した方が増えたことから、住宅確保給付金の適用範囲は以前よりも柔軟になっています。そのため、失業中の方や収入の低い世帯の方は、自治体の自立支援サービスが活用できないか、ぜひ一度確認してみてください。
家賃の支援に加え、就労支援や生活相談など、包括的なサポートを受けられる可能性もあります。生活の再建に向けて一歩を踏み出すために、早めの相談が重要です。

↑↑バナーをクリックして読者様アンケートへ!是非あなたの体験をお聞かせください☆
引越しに活用できる助成金制度

ここまでご説明したとおり、この国には新婚世帯やひとり親世帯、失業中の方々を助けるさまざまな制度が用意されています。この章ではその中で実際に引越しに関連する助成金支援制度についていくつかご紹介させていただきます。
なお助成金制度は募集期間や該当条件が詳細に定められており、募集期間が終了している場合もあります。また対象者の条件が変更になるケースも少なからずございます。従って気になる助成金制度を見つけた場合は、必ず詳細についてご自身の目で最新情報をお調べください。
結婚新生活支援事業
結婚新生活支援事業とは、経済的理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象にした経済的支援制度。新居の購入費や初期費用、引越し費用にあたる金額を支給してくれます。婚姻に伴う新生活を経済的に支援することで、地域における少子化対策の強化を目的としたものです。
| 対象者 | 【下記の条件をすべて満たす世帯】 ・該当する市区町村にお住まいで、支援事業終了日までに入籍した世帯 ・世帯年収が該当条件以下である(※市区町村で異なる) ・年齢が該当条件以下である(※市区町村で異なる) ・その他、市区町村が定める要件を満たしている (※住所を管轄する市役所で、諸条件を確認してください) |
| 費用対象 | 新居の購入費 新居の家賃・敷金や礼金・共益費・仲介手数料 新居への引越し費用 |
| 補助金 上限額 | 30万円〜60万円(年齢や自治体によって異なる) |
| 申請方法 | 市区町村に確認の上で直接申請をする |
住居確保給付金
生活困窮者自立支援制度の1つとして、住居確保給付金が用意されています。こちらは市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月間(延長は2回までで最大9ヶ月間)支給するというもの。最近では新型コロナウイルス感染拡大で離職や減収に見舞われた方が増加したため、住居確保給付金の期間を延長しています。現在失業や離職で減収して経済的に困っている方は、こちらが適用できないかを確認してみましょう。
| 対象者 | ・離職や廃業して2年以内であること(※同程度まで収入が減少していること) ・世帯収入の合計額が各市町村民税基準額と家賃の合計額を超えていないこと ・世帯の預貯金額が一定基準額を超えていないこと ・誠実かつ熱心に求職活動をしていること(※ハローワークへの求職申込・職業相談・企業面接) |
| 費用対象 | 家賃 |
| 補助金 上限額 | 1人世帯:53,700円 2人世帯:64,000円 3人世帯:69,800円 (※上記の金額は東京都の場合) |
| 申請方法 | 市区町村に確認の上で直接申請をする |
移住支援金
都市部から地方へ移住する人を対象に、引越しや住宅取得の費用を補助する「移住支援金」制度が注目されています。これは政府と自治体が連携して実施する地方創生施策で、2025年現在も継続中です。
| 対象者 | ・東京圏などから地方に移住する人 ・移住先の地域で就業・起業・テレワークなどを行う人 ・地域要件・収入制限など、自治体の基準を満たすことが条件 |
| 費用対象 | 引越し費用・住居取得費などにも活用可 |
| 補助金 上限額 | 単身の場合:最大60万円 世帯での移住:最大100万円以上(子ども加算あり) ※自治体ごとに対象条件や補助額が異なります |
| 申請方法 | 事業を実施する都道府県・市町村に問い合わせをする |
住宅ローン減税
住宅ローン減税は一定の条件を満たした住宅を購入・リフォームした場合に、所得税や住民税の一部が還付される制度です。確定申告や年末調整の際に、年末の住宅ローン残高1%に相当する所得税が10年間(または13年間)控除されます。
| 対象者 | 【対象者の条件】 ・住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること ・特別控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である ・10年以上の住宅ローンを組むこと ・居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと 【住宅の条件】 〈新築住宅〉 ・対象住宅の床面積が50㎡以上であること(合計所得1,000万円以下の場合は40㎡以上でも申請可能) ・省エネ基準適合が必須(2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅) ・床面積40㎡以上50㎡未満は合計所得1,000万円以下かつ2025年末までに建築確認を受けた場合のみ適用 〈既存住宅(中古)〉 ・床面積50㎡以上 ・新耐震基準適合または以下のいずれかの証明書が必要:(※築年数によって異なります) →耐震基準適合証明書 →住宅性能評価書(耐震等級1以上) →既存住宅売買瑕疵保険加入 ・省エネ基準適合は不要(ただし、省エネ性能により借入限度額に差がある) |
| 費用対象 | 所得税の控除 所得税で控除しきれない場合のみ住民税から控除 |
| 補助金 上限額 | 年末の住宅ローン残高×0.7%が控除額 住民税からの控除が入る場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限9.75万円) |
| 申請方法 | 初年度申請方法 確定申告(税務署への申告)が必要 2年目以降申請方法 会社員:年末調整で申請可能 個人事業主等:確定申告が必要 |
(参照:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001890680.pdf)
【東京23区内】引越しに活用できる助成金制度の例

ここまで全国的に利用できる引越しに関する助成金制度についてご紹介しました。
こちらに加えて都道府県や各自治体ごとにも引越しに関する助成金制度が定められていることがあり、住む予定の地域における取り組みを把握したうえで転居先を選ぶ際に比較検討することも重要です。
たとえば東京23区内でもさまざまな助成金制度が実施されており、区によって受けられる支援が細かく異なっています。
各区でどのような支援が受けられるのかを把握してもらえるよう、引き続き東京23区で実施されている助成金制度の例についてご紹介していきます!
なお、助成金制度は予算に限りがあり、予定していた募集数に達すると受付終了となることが多く、最新の情報は区のホームページで確認したうえで利用を検討してみてください。
新宿区 次世代育成転居助成
次世代育成転居助成金制度は、子育て世帯が新宿区内で賃貸住宅を住み替える際の費用負担を軽減するためのものです。新しい家族が増えたり、子どもが成長したりして部屋が狭くなり、住み替えを検討する際に助成金を受け取れる制度です。
次世代育成転居助成は、募集世帯数が限られており先着順となっています。そのため、条件に該当する場合は、速やかに新宿区役所の関連窓口にお問い合わせをしてみてください。
| 対象者 | ・義務教育修了前の児童を扶養して同居する世帯(※出産予定の場合は、出生の事実を証明する必要がある) ・1年以上新宿区に居住していること ・住民税の滞納がないこと ・家賃滞納をしていないこと ・その他の公的住宅扶助を受けていないこと ■ 住宅要件 転居後の住宅が新耐震基準に適合していること 転居後の住宅の家賃が次の金額以下であること。 世帯人数…家賃額 4人まで…180,000円 5人まで…215,000円 以降6人以上の場合は1人につき3万5千円を加算する。 ■ 所得要件 前年中の世帯の総所得が、次の金額以下であること。 扶養親族の人数…所得金額 1人…5,400,000円以下 2人…5,780,000円以下 3人…6,160,000円以下 4人…6,540,000円以下 5人…6,920,000円以下 ※以降、6人以上の場合は、1人につき38万円を加算する。 |
| 費用対象 | 転居前後の家賃差額分 引越し代金 |
| 補助金 上限額 | 家賃差額助成金:35,000円 引越し代金:100,000円 (※家賃差額助成金は最長2年間) |
| 申請方法 | 新宿区役所に確認の上で直接申請をする |
新宿区 多世代近居同居助成
多世代近居同居助成金制度は、子世帯と親世帯が新宿区内で近居または同居する際の住居費用の負担を軽減するものです。経済的負担を軽減することにより、近居・同居を推進して、互いが支え合える安全安心な住宅確保の支援および住環境の向上を目指します。
| 対象者 | 【下記のいずれかに該当する方】 ・65歳以上の方を含む60歳以上の方のみで構成する世帯 ・要介護1~5または身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方を含む世帯 ・義務教育修了前の児童を扶養して、同居している世帯 【下記の条件を全部満たす方】 ・世帯年収が一定以下の方 ・親世帯か子世帯が新宿区内に1年以上居住していること ・住民税を滞納していないこと ・その他の公的住宅扶助を受けていないこと ・区外から転入する世帯は、過去6か月間に区内に居住したことがないこと ・外国人の場合:在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること ・住戸専用部分の面積が、次の面積以上であること。 →単身:25㎡ →2人:30㎡ →3人以上:(10㎡×世帯人数)+10㎡ |
| 費用対象 | 不動産登記費用・礼金・権利金・仲介手数料・引越し代金 |
| 補助金 上限額 | 複数世帯最大20万円まで 単身世帯最大10万円まで |
| 申請方法 | 新宿区役所に確認の上で直接申請をする |
新宿区 住み替え居住継続支援
住み替え居住継続支援は、新宿区内の民間賃貸住宅の取り壊しなどにより転居を余儀なくされた時に、転居費用の一部を支給してもらうための助成金です。
なお、転居先は新宿区内に限定されています。転居先の賃貸住宅の賃貸人と契約を結ぶ前に支援予定登録申請が必要です。
| 対象者 | ・取り壊し、売却、賃貸事業の廃止などを理由に家主から立退きを求められた場合 ・定期建物賃貸借契約の終了による立退きは除く ・自主的な転居は対象外 【高齢者世帯】 65歳以上のひとり暮らし世帯あるいは60歳以上の方だけで構成する65歳以上の方を含む世帯 【障害者世帯】 身体障害者手帳4級以上の方、愛の手帳3度以上の方あるいは精神障害者保健福祉手帳を所持する方を含む世帯 【ひとり親世帯】 18歳未満の児童とその児童の父あるいは母だけで構成する世帯 |
| 費用対象 | ・転居によって家賃が上昇した場合の上昇分の一部 ・引越し費用の一部 |
| 補助金 上限額 | 【家賃差額に係る支援の限度額】 単身世帯:36万円 2人以上世帯:54万円 【引越し費用に係る支援の限度額】 15万円 |
| 申請方法 | 新宿区役所に申請書と添付書類などを提出する |
新宿区 民間賃貸住宅家賃助成
民間賃貸住宅家賃助成は、義務教育修了前の子どもを扶養している世帯を対象とした家賃支援制度です。子育て世帯の経済的負担を軽減し、安定した住生活を支援することを目的としています。
| 対象者 | ・義務教育修了前の子どもを扶養している世帯 ・世帯年収が520万円以下であること ・新宿区内に1年以上居住していること ・住民税を滞納していないこと ・月額家賃が、22万円以下であること(管理費・共益費は含みません) ・家賃を滞納していないこと。 |
| 費用対象 | 家賃の一部 |
| 補助金 上限額 | 月額3万円まで(※最長5年間) |
| 申請方法 | 新宿区役所に確認の上で直接申請をする |
(参照:https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file07_02_00001.html)
北区 ファミリー世帯転居費用助成
東京都北区では18歳未満の子どもを2人以上扶養している世帯を対象とした転居費用の助成制度です。繁忙期である3月や4月の転居であっても、この制度を活用することで費用を抑えることができます。
| 対象者 | ・18歳未満の子どもを2人以上扶養している世帯 ・北区内に1年以上住民登録をしていること ・世帯年収が一定基準以下であること ・住民税を滞納していないこと ・区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居したこと |
| 費用対象 | 礼金・仲介手数料の合算額 |
| 補助金上限額 | 上限30万円まで |
| 申請方法 | 北区役所に確認の上で直接申請をする |
豊島区 子育てファミリー世帯家賃助成制度
子育てファミリー世帯家賃助成制度とは、豊島区内の良質な民間賃貸住宅に転居した場合に、転居後の家賃と基準家賃との差額を助成する制度です。一定の要件を満たす子育てファミリー世帯が対象となります。
| 対象者 | ・令和7年4月1日以降、区外からの転入および申請は原則として対象外 ・15歳未満の子どもを扶養している世帯 ・令和7年4月1日現在豊島区内に住所を有し、かつ、区内に引き続き1年以上(令和6年3月31日以前から)住民登録をしていること ・世帯年収が一定基準以下であること ・住民税を滞納していないこと ・前年の世帯の月額所得が338,000円以下であること ・住み替え後の家賃が月額170,000円以下(共益費を除く)であること |
| 費用対象 | 家賃の差額助成 |
| 補助金 上限額 | 月額上限3万円 |
| 申請方法 | 豊島区役所に確認の上で直接申請をする |
墨田区 民間賃貸住宅転居・転入支援
墨田区では、未就学児を扶養している世帯を対象とした転居・転入支援制度があります。家賃10万円以上の物件への転居時に、支援を受けることができます。
| 対象者 | ・未就学児(6歳未満)を扶養している世帯 ・家賃10万円以上の物件への転居 ・墨田区内への転居または転入 ・世帯年収が一定基準以下であること ・平成 30 年4月1日以降に転居又は転入すること ・住民税を滞納していないこと |
| 費用対象 | 礼金・仲介手数料・引越し代金 |
| 補助金 上限額 | 各項目につき最大12万円 |
| 申請方法 | 墨田区役所に確認の上で直接申請をする |
千代田区 次世代育成住宅助成
千代田区の次世代育成住宅助成金制度は親世帯との近居のために住み替える新婚世帯や子供の成長のために広い住宅に住み替える子育て世帯を対象に、住宅費用を助成する制度です。区内の世帯構成のバランス改善や地域コミュニティの活性化、定住化の促進を目的としています。
| 対象者 | 1 親元近居助成 区内に引き続き5年以上居住する親がいる新婚世帯または子育て世帯 区外から区内への住み替えまたは区内での住み替えをする。 2 区内転居助成 区内に引き続き1年以上居住している子育て世帯 義務教育修了前の子どもを扶養している世帯 区内での住み替えをする |
| 費用対象 | 転居に伴う諸費用 |
| 補助金 上限額 | 上限8万円まで |
| 申請方法 | 千代田区役所に確認の上で直接申請をする |
(参照:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/sumai/jose/jisedai.html)
目黒区 ファミリー世帯家賃助成
目黒区のファミリー世帯家賃助成金制度は、18歳未満の子を扶養する世帯に対して、家賃を助成する制度です。目黒区内での居住の継続と子育ての支援を行うことを目的としています。
| 対象者 | ・18歳未満の子どもを扶養している世帯 ・目黒区内に1年以上居住していること ・世帯年収が一定基準以下であること ・賃貸借契約者が申請者本人、配偶者等または親族である 【住宅の条件】 月額家賃が5万円以上18万円以下である |
| 費用対象 | 月額家賃の一部 |
| 補助金 上限額 | 上限2万円まで(※最長3年間) |
| 申請方法 | 目黒区役所に確認の上で直接申請をする |
杉並区 転居費用助成
杉並区では、所得が一定の基準以下の方の引越しにあたっての引越し代金や、引越しに関わる初期費用を負担してくれる支援制度があります。
| 対象者 | ・引き続き2年以上区内に居住し住所を有していること ・区内の民間賃貸住宅に居住していること ・住環境の改善の為の転居、もしくは現状より安い家賃の住宅への転居を希望していること ・世帯の合計所得金額が月額158,000円以下(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯は、月額214,000円以下)であること |
| 費用対象 | 建物賃貸借契約締結に係る費用(敷金、家賃、共益費分を除く) 転居先への家財の運搬費用 |
| 補助金 上限額 | 単身世帯:上限15万円 2人以上の世帯:上限20万円 |
| 申請方法 | 大田区役所に確認の上で直接申請をする |
特定優良賃貸住宅(各自治体主催)
特定優良賃貸住宅とは、中堅所得者のファミリータイプの賃貸住宅のことをいいます。良質な住宅を軽い負担で借りることができることが最大の魅力です。「UR賃貸住宅」「公社賃貸住宅」と運営母体によって呼び方が異なります。
特定優良賃貸住宅に住むためには、各自治体が設ける入居条件の基準をクリアする必要があります。入居条件は各自治体で異なるため、お住まいの地域を管轄する自治体へお問い合わせをしてみてください。
(参照:https://www.homemate.co.jp/guide/navi/family/point/012.html)
まとめ
この記事では住まいに関する代表的な助成金制度をご紹介させていただきました。自治体の助成金制度は今回東京都の事例を取り上げさせていただきましたが、それ以外の全国の市区町村でもそれぞれ助成金制度は用意されています。
ただし当然、助成金は誰もが受けられるわけではありません。ただ「費用が安くなればいいや」というお気持ちの方は申請を却下されてしまう可能性がありますが、本当に困っている方にはきっと手を差し伸べてくれることでしょう。
口コミやインターネットで情報を探すことも重要ですが、最も確実なのは直接市町村役所や都道府県の窓口で相談することです。ガスや電気、水道などの設備に関する設置費用も含まれる場合があるため、一括で相談することをおすすめします。
それぞれ基本的に相談窓口は各自治体となっていますので、現在お住まいの地域の市役所で活用できる助成金制度がないか、自分の利用できる制度がないかを一度お調べになってみてください。
いま現在、引越し費用のことでお悩みをお持ちの方々にこの記事がご参考になれればと思います。
カルガモ引越しセンターは業界最安クラスのプランを提供している引越し業者です。
引越し料金を安く抑えたいという方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

↑↑バナーをクリックして読者様アンケートへ!是非あなたの体験をお聞かせください☆